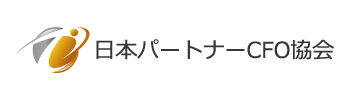ベンチャー企業の社外取締役としての役割を全うするべく、MBA、パートナーCFOと研鑽を重ねる女性会計士
ナイル株式会社社外取締役(常勤監査等委員)・公認会計士
大村 尚子(おおむら なおこ)さん

今回ご紹介するのは、パートナーCFO養成塾の第4期生(2021年6月~11月)の大村尚子さんです。
大村さんは監査法人で16年の経験を経て、ベンチャー企業の常勤社外監査役へキャリアチェンジ。監査役として経営に関わる中でMBA、パートナーCFOと自己研鑽を続けてこられました。公認会計士の専門性と社外取締役の経験を持つ大村さんにとって「CFOは憧れの存在」だったそうですが、養成塾での学びを機に「一歩踏み出せばできそう」と思えるようになったそうです。そんな大村さんが考えるパートナーCFOと社外取締役の共通点や、社外取締役として具体的に気を付けていることを含めてお伺いしました。
【プロフィール】
社外取締役(常勤監査等委員)・公認会計士
中央大学商学部卒・公認会計士。1997年、監査法人トーマツ入所し、製造業、サービス・流通、大手商社・銀行など多種多様な業種の金商法・会社法監査をはじめとし、米国基準、IFRS基準の会計監査や公開支援業務等に従事。近年は、監査業務と監査管理ソフトや監査用ツールの導入・教育研修業務を兼務。2013年10月、16年間勤務した監査法人トーマツ退所し、同年11月にナイル株式会社社外監査役に就任。2015年5月、監査等委員である取締役(常勤)、社外取締役に就任(現任)。他社で非常勤監査役を兼任。2020年春にはMBA(経営学修士)を取得。
(ナイル株式会社)
2007年創業。「幸せを、後世に。」をミッションに掲げ、デジタルノウハウを強みに、マーケティングDX事業と自動車産業DX事業を展開。
事業内容:マーケティングDX事業、自動車産業DX事業
資本金:3,674,556,838円(含、資本準備金等)
代表者:代表取締役社長 高橋 飛翔
URL:https://nyle.co.jp/
経済的自立を目指して公認会計士の道へ
そもそも会計士を志したきっかけは何でしょうか。身近な方にいらっしゃったのですか。
家族背景からお話しますと、私の父親はサラリーマンで、母親は洋裁の仕事をしていています。私は3人姉妹の末っ子で、父親は物心ついたころから私たちに「手に職をつけろ」と言っていたんです。「女性も経済的に自立せよ」という事なのだなと思い、高校生の頃から「資格が必要な仕事が一番経済的な自立につながりそうだから、何か資格を取ろう」と考えていました。
当時はインターネットでの情報収集が今ほど一般的ではなく、職業と言っても親が知っている職業の中から選んでいたところがありました。弁護士か医者か、隣の幼馴染のお父さんが税理士だったので、税理士か、といった具合です。私の場合も「何かやりたいことがあって会計士を選んだ」というのではなく、中央大学の付属高校から中央大学の商学部会計学科に進学したところ、「資格と言えば会計士」という環境だったことから選択しました。ちなみに、6歳上、4歳上の姉たちは、デザイナーになったり、洋服のパターンを作ったりするアパレル、ファッション系の仕事に就いていて、私だけが違う方向に進みました。 私が卒業した頃はちょうど就職氷河期でしたが、卒業後2年目に公認会計士試験に合格し、その後監査法人のトーマツに16年勤めました。
人生80年時代。後半戦に向けて、活躍の場を監査法人からベンチャー企業へ
大村さんは40歳を節目にキャリアチェンジを考えられたそうですね。
はい。私がいた部署は、国内のクライアントがメイン。労働時間は決して短くはなかったですし、出張があったりとハードなスケジュールでした。オープンな社風で上司や先輩も気さくで良い人が多く、仕事自体は全然苦になりませんでしたが、当時は「人生80年時代」と言われていて、40歳になる2、3年前から「後半戦で何をするかな」とキャリアチェンジを考え始めました。
監査法人を辞められてすぐに、ナイル株式会社(注)(当時はヴォラーレ株式会社。以下、ナイル。)の常勤監査役に就任されたとのことですが、キャリアチェンジとしてベンチャー企業の常勤監査役を選ばれた理由や具体的なきっかけを教えてください。
実は次の仕事が決まったから会社を辞めたわけではなく、「40歳を節目に会社を辞める」ということだけは先に決めていたんです。ちょうどそのころ、監査法人の元同僚から「自分が非常勤で入っている先で常勤監査役を探しているが興味ある人はいないか」という連絡がありました。
今でこそ、監査役をする女性の公認会計士の方も増えてきていますが、当時監査法人の仕事で見てきた企業では、「監査役といえば年配の男性」だったこともあり、正直なところ自分のキャリアの選択肢としては考えていませんでした。その後の会話の中で、近況報告のつもりで「私もそろそろ(監査法人を)辞めるんです」という話をしたところ、「じゃあここの監査役やってみたら?」とお声掛け頂きました。
なるほど、元同僚の方からの話がきっかけだったのですね。
そうですね。想定外のキャリアチェンジではありましたが、元同僚がいるなら大丈夫だろうと思えたこともあり、常勤監査役(※2015年から「社外取締役(常勤監査等委員)」)の仕事を決めました。
社外監査役としての働き方:企業の成長に応じて週3から週5勤務へ
ナイルでの社外監査役としての働き方やスケジュールを教えてください。
ナイルに入社した当時は週3勤務でしたが、その後企業の成長に伴い監査の時間も増えたこともあり週5勤務へ切り替えています。
常勤なので基本的に週5日対応していて、経営会議や経営幹部との定例ミーティングに参加しています。コロナ禍以降は基本在宅ですが、それ以前は出社していました。
大村さんが在籍されてからのナイルの成長とは、具体的にどのようなことでしょうか。
一番は社員数と事業数が増えたことです。私が入社した時は、総勢60名だったスタッフが、現在は派遣や業務委託含め約300名を超える会社になりました。
役員に関しては、特に執行役員を去年から増やしているので、経営層はだいぶ厚くなってきています。執行役員は新卒入社も中途入社もいて、ミックスされているのがいいところだと思います。
そうしたナイルの変化の中で、社外取締役として取り組んでいることや心がけていることを教えてください。
業務執行している役員や現場のメンバーは目の前の業務に寄ってしまいがちです。なので、私は世の中のトレンドや、緊急性はないが長期的に見て重要なアジェンダを投げかけるように心がけています。
一つの企業に長く勤務していると相互に信頼関係が出来るのはいいところですが、一方で、客観性を失わないよう気を付けています。現場へ配慮はしつつ、必要なことは言うようにしています。役員同士は普段はフランクに冗談を言い合える間柄ですが、会議では真剣に議論しています。
社外取締役としてのやりがいは、どういったことで、どのような場面で感じますか?
他の役員や社員から感謝されたり、自分が役にたったなと思える時です。ナイルでは役員間で360度評価をしているので、自分へのフィードバックはそこで得られますね。

経営者の意識と社外取締役の力で作られる、コーポレートガバナンスの実態
大村さんは監査役をされているということで、コーポレートガバナンスに関してもお伺いします。今年は東証の上場区分の変更がありますが、今後に向けて今から準備されていることがあれば教えてください。
ナイルの場合は、結構前からそのあたりのガバナンスを利かせる意識があって、社外役員が半数以上です。ダイバーシティという観点では、今は女性としては私が入っています。また、今後海外にも展開するようなフェーズになれば、やはり外国人の方のボードメンバーも必要になるのかなとは思います。
そのあたりは創業社長がもともと意識をお持ちということでしょうか。
そうですね。社長は私から見ても、社外の知見を取り入れるのがすごく上手だなと思います、社外役員として招聘したり、アドバイザーという形で、必要なタイミングで必要な方の助言をもらったりされています。
スタートアップで、上場前にこれだけ色々な体制を整えられている会社ってすごくしっかりしているなと思い、大村さんも相当力を発揮されているのではないかと思います。
そこはどうでしょうか(笑)。取締役会での議論はかなり活発で、社外取締役の皆さんが、それぞれの見地から積極的に意見していただけるので、そういったところでガバナンスがちゃんときいているのではないかなと思います。
ナイル以外での非常勤監査役としての働き方
ナイル以外での非常勤監査役としての仕事としては、どのような働き方をされているのでしょうか。
今はナイルの他は1社で非常勤監査役をしていて、そこは3年継続しています。月に1回、監査役会と取締役会が同日に開催されるので、会社に訪問してリアルで出席しています。
MBA、パートナーCFO……社外取締役として自己研鑽を続ける理由
大村さんはパートナーCFO養成塾に来られる直前まで、MBAに通われていたとお聞きしています。社外監査役として経営に関わることが多かったから興味を持ったという事でしたが、その背景を教えてください。
ナイルに入社して4~5年が経った2018年に、グロービスの単科生として受講しはじめました。その背景としては、監査役として関与し始めてすぐ、経営会議で資金調達に関して優先株式の話や株式の条件など、様々な話題が出たことがありました。会計士としてアカウンティングや経理の話は分かりますが、ファイナンスは正直勉強しない限り分からないことが多くて……。このままではいけない、しっかりと学びたいなと思うようになりました。また、経営上の課題として組織や人に関することも話題になるので、そこも体系的に学びたい…それならばMBAが一番体系的に学ぶのによさそうだと思い至りました。
実際に監査法人を退職された先輩や後輩でMBAを取得した方が周りにいたので、私も考えてみようかなというきっかけになりました。
大村さんはすでに社外監査役をされていて、更にMBAにも通われていたとのことですが、そもそもパートナーCFOに興味を持ち、オープンセミナーに来たきっかけは何でしょう?
元々CFOという仕事に興味はあったものの、具体的に仕事をするにはどうしたらいいかと考えていて、少しずつ情報収集をしていました。
高森さんの存在を知ったのは、2019年に開催されたグロービス経営大学院のあすか会議というイベントがきっかけです。そこでパートナーCFO養成塾2期生の水野さんのお話を聞く機会があり高森さんのことを知りました。
2019年のオープンセミナーに参加されて、実際に養成塾に通われたのは2021年でしたね。
そうですね。2019年はまだグロービスに通っていたので、両方やるのはちょっと大変かなと思ったので、まずはMBAを卒業してからパートナーCFOを考えようと思ったんです。元々学ぶことは好きで、全然苦にならない方なので。
オープンセミナーに参加されて、MBAとはまた違う学びが得られそうだと思われたということでしょうか。
そうですね。MBAで学んだり、ナイルで見てきたエクイティ・株式資本での資金調達は結構馴染みがありましたが、デット・借入に関してはよくわからないこともあったので、そういった多様な資金調達手段も含めてインストールするなら、CFO養成塾がいいのかなと思いました。実際に受講してみると、高森さんの実務執行力が高いためだと思いますが、パートナーCFOの業務が多岐にわたるので、思ったより範囲が広くてびっくりしました(笑)

ビジネスでキャリアと強みが一つあれば、金融の専門家でなくともパートナーCFOを目指せるという気づき
実際に養成塾を受講されて、印象に残っていることなどあれば教えてください。
受講前は、金融に強い人が集まっているイメージもありましたが、実際には意外と幅広く色んなキャリアの方がいらっしゃったことに驚きました。中小企業診断士、税理士の方や事業会社の中でキャリアを積んでこられた方など…受講生の皆さんと話す中で、「金融の専門家に限らず、ビジネスでキャリアを積んでこられて、(CFO8マトリックス®に)自分の強みが何か一つあれば、そこを軸にパートナーCFOとして目指せるんだな」という気づきがありました。
養成塾での学びとMBAでの学びで共通しているところや違うところがあれば教えてください。
共通するのは、会社の成長段階でどのような課題が生まれるか、それにどう向き合えばいいかを学ぶところですね。MBAでは扱わない内容で、特に養成塾で特徴的だったのは、中小企業経営に必要な知識や補助金の活用が含まれていたことです。こうした中小ベンチャー企業支援の実務に役立つ知識が学べるのが養成塾の特徴だと思います。
やはり、補助金や助成金については知っているかどうかは大きな違いになると思いますし、補助金を前提に展開するビジネスがあることも初めて知りました。実際に要件を満たしていても知らないことには使えないので、今は補助金や助成金について知らないともったいないな、と思います。
パートナーCFOと社外取締役に共通するのは客観性と中立性
社外取締役とパートナーCFOについてお伺いします。今後さらにパートナーCFOが増えてくる中で、パートナーCFOから社外取締役として会社の経営に深くかかわっていきたいという方、目指される方も出てくると思います。大村さんが考える、社外取締役とパートナーCFOの共通点や相違点を教えてください。
両方とも経営全般をカバーしている点では共通していると思います。それから、現場や執行サイドからは一定の距離を保っているので、客観性、中立性という点も共通するところですね。
相違点は、パートナーCFOはクライアントの希望やご自身のスタンスによるものではありますが「業務執行をある程度やってもいい」というところでしょうか。社外取締役は、それはできません。パートナーCFOの場合は、深くかかわっている場合はご自身が手を動かす部分も増えてくると思いますので、そこが大きな違いかなと思います。
パートナーCFOから社外取締役となる場合に、留意するべきことにはどんなことがありますか。
パートナーCFOとして関わっている先に対して、その後、社外外取締役として関わっていくことはできると思います。ただ、社外取締役は会社法に規定されているものなので、より責任は重いように感じます。パートナーCFOとして会社を見ている分、会社の状況を分かっているとは思いますが、そのうえで客観性を持ってアドバイスする必要があります。
上場後は、しっかりと取締役として責任を果たさなければ訴えられる可能性もあります。私自身、緊張感を持ってちゃんと会社のことを見て、言うべき時は言わないと、自分の身にもリスクがあるなと思いながら仕事をしています。
中立性や客観性に関しては、どこまで執行側に踏み込むか、絶妙なバランスが必要だと思います。社内の人との人間関係や接し方に関して、例えば人間関係が出来るまでは手控える等留意されていることはありますか。
変に空気を読んで、思ったことを手控えてしまっては監査役としている意味がないと思っているので、会社が置かれている状況や、伝え方に気は配りつつも、言うべきことは言うようにしてきましたし、今もそのへんは気を付けています。
自分の発言に対して、反論されることは過去にもありましたし、今もありますが、それはお互いにちゃんと言うべきことを言ったうえで「どうするのか?」、という建設的な話ができていればいいのかなと思います。
養成塾の学びを機に、CFOは“憧れ”から“一歩踏み出せばできそう”な存在に
養成塾の最後で、社外取締役としての仕事や、これから新たにパートナーCFOとしても活動してみたいというお話があったかと思います。今後について、養成塾の学びをどう活かしていきたいのか、改めて教えてください。
社外取締役としての仕事の一環で、執行役員以上の方とは毎月1回30分程度個別面談しています。毎月のことなので、一人当たり年に12回。せっかくなら有意義にその時間を使いたいと考えています。
Day3ではコーチングのセッションがありましたが、周りからも「面談する機会が多いなら、エグゼクティブコーチングを学んでみたら?」と言われることも。私がコーチングをしっかり学ぶことで、周りの方の成長や会社の成長にもつながると思うので、検討中です。
養成塾を終えてからの変化や、大村さんの中長期的なキャリアプランを教えていただけますか。
パートナーCFO養成塾の前は、CFOはちょっと憧れのような感じでした。養成塾でCFO業務の内容に関して知識をインプットできたことで、憧れからより身近に感じるようになり、自分に引き寄せて考えられるようになったのは大きな変化ですね。
元々は「分からないが故のあこがれ」みたいなもので、CFOにこだわっていたところがありましたが、今はそのこだわりがなくなりました。自分のこれまでの経験をベースに役に立てるのであれば、肩書は社外取締役でも、監査役でも、パートナーCFOでも、こだわる必要はないなと。魅力的な会社や経営陣の方たちと一緒にお仕事ができるのであれば、そのほうが重要だなと思うようになりました。 また、実際に養成塾を修了された方の具体的な活動内容を伺って、それぞれの強みを活かして皆さん頑張っていらっしゃるので、私の中にあったCFO像よりも身近な感じがして、ハードルを感じなくなり、ちょっと一歩踏み出したらできそうだなと感じるようになりました。何か、いい機会があればやってみたいですね。
大村さんはどんな会社や人が魅力的だと感じますか。
常に変化をいとわずに新しいものを生み出していくとか、挑戦を恐れないとか、スピード感があるとか、ある程度アグレッシブなほうが好きですね。
ちなみにナイルでは常に新しいことをやっているので、同じ会社にはいるけれども、常に新鮮な気持ちで仕事をしています。もう1社の非常勤監査役をしている会社も創業社長の方がすごくスピード感があって、時にサプライズもありますが、面白いですね。安定よりも変化がある方が楽しさを感じます。
そうすると、今のようなお仕事は、大村さんにとって人生の後半をかけていくに値する、やりがいのある仕事、ということでしょうか。また、現在は社外取締役(常勤監査等委員)という立場ですが、今後執行側に回ることや起業は考えられたりしませんか。
はい。ただ、そろそろ10年経ちますし、今は「人生100年時代」。となると、またこの先、今と同じことだけを続けていくと自分自身の成長もないと思いますので、色々考えているところです。起業も興味はあって、一度やってみたいなとも思いますが(笑)。
金融の専門性に限らず、興味ある人へパートナーCFOへの門戸は開かれている
P-CFO養成塾を終えてみて、どういった方におススメでしょうか。
これまでのご自身のキャリアの中で、何か一つでも強みがあって、CFOの仕事に興味があれば、金融の専門性が必ずしも高くなくとも、パートナーCFOへの門戸は開かれていると思います。あまり構えずに、興味があればおすすめです。
日本パートナーCFO協会のメンバーとなりましたが、今後の意気込みがあれば一言お願いします。
今協会でやっていただいているP-CFOサロンなどは有益だと思うので活用していきたいです。また、我々パートナーCFOが実際に活動することで、パートナーCFOの認知度向上につながればと思います。そうしてビジネス界隈で認知度を上げていくと、より活動もしやすくなるのではないかなと考えています。
認知度アップ、みんなで頑張りましょう!という気持ちです。
なるほど、皆さんのパートナーCFOとしての活躍と認知度向上、この二つは両輪ですね。今回の大村さんのインタビューも、認知度向上につながるものと思います。改めて、本日は貴重なお話をありがとうございました。

(編集後記)
公認会計士としての豊富な経験を持ち、現役のベンチャー社外取締役としてすでにご活躍中ながら、「どうすれば、もっと自分が周囲にプラスとなるか」を常に考え、学び続ける大村さんの姿勢に大変刺激をもらいました。また、自分にとって魅力的な会社や人とは何かを明らかにし、自分のタイミングでキャリアの転機を作っていくことは、老若男女問わず大切な考え方だなと思います。
養成塾を経て「肩書にこだわらず、魅力的な会社や経営陣の方たちと一緒にお仕事ができることが重要」と語る大村さんの表情に気負いはなく、どこかリラックスした軽やかさが伝わってきました。大村さんの今後益々のご活躍を、心より応援しております。

<取材・文>第2期生 溝上愛
取材日:2022年2月15日